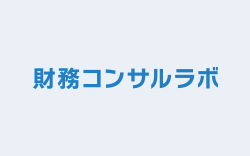- HOME
- ブログ
- 店・会社・事業の『売却』及び『廃業』
- 事業承継におけるM&Aの重要性と実績を解説した記事です。従業員の雇用維持とシナジー効果を見逃すな!
事業承継におけるM&Aの重要性と実績を解説した記事です。従業員の雇用維持とシナジー効果を見逃すな!

目次
はじめに
今日の日本社会においては、少子高齢化の進行に伴い、企業の事業承継問題が重大な課題となっています。親族内での後継者選定が難しくなる中、M&A(企業の合併・買収)が注目される新たな選択肢です。本稿では、事業承継におけるM&Aの重要性と実績について、詳しく解説していきます。
M&Aによる事業承継のメリット
事業承継におけるM&Aには、多くのメリットが存在します。まず、後継者不在の問題を解決することができます。また、従業員の雇用維持や既存の取引関係の継続も可能になります。さらに、M&Aを行うことで両社のシナジー効果が発揮され、事業の発展や拡大につながるでしょう。
後継者問題の解決
親族内に適切な後継者がいない場合、M&Aを選択することで、外部から優秀な経営者を獲得することができます。経営資源を円滑に引き継ぐことができるため、事業の持続的な成長が期待できます。
中小企業庁の調査によれば、2021年時点で約半数の中小企業が後継者不在の状態にあります。M&Aは、そうした企業にとって有効な事業承継手段といえるでしょう。
従業員の雇用維持と取引関係の継続
M&Aにより、従業員の雇用が確保されます。また、既存の取引先や顧客との関係性も引き継がれるため、事業の継続性が担保されます。これらは、企業経営において極めて重要な要素です。
一方、親族内承継や従業員承継の場合、経営のノウハウや情報が不足することがあり、従業員の雇用や取引関係の維持が困難になることがあります。
事業シナジーの創出
M&Aを行うことで、両社の強みを掛け合わせたシナジー効果が期待できます。例えば、製品やサービスの補完、販路の拡大、技術力の向上などが考えられます。
中小企業にとって、単独での事業展開には限界があります。M&Aによって経営資源を結集させることで、より大きな事業機会を獲得できるでしょう。
M&Aによる事業承継の実績
政府による後押しもあり、近年のM&Aによる事業承継の件数は増加傾向にあります。国内のM&A市場規模は拡大を続けており、地方自治体や金融機関、民間企業などが連携して支援に取り組んでいます。
M&A件数の推移
2022年の国内M&A件数は過去最高の5,199件とのことです。そのうち、事業承継型のM&Aは748件で、2021年の705件から6%増加しています。
内閣府が発表した最新の『中小企業白書』によれば、後継者不在率は2012年の約49%から2022年には約37%まで低下しており、M&Aの活用が後継者不在の企業の減少に寄与していることがうかがえます。
公的支援の拡充
政府は、事業承継税制の拡充や事業承継支援センターの設置など、中小企業のM&Aを後押しする施策を講じています。各自治体でも、地域の企業のM&A支援に乗り出す動きが広がっています。
また、中小企業基盤整備機構や民間のM&A仲介会社などが、企業のマッチングから手続きまでをサポートしており、M&Aへの参入障壁が低くなってきています。
地域活性化への波及効果
地方の中小企業においても、M&Aによる事業承継の動きが活発化しています。地元の雇用維持や伝統産業の継承につながることから、地方創生の観点で重要な取り組みとなっています。
一方で、M&Aの専門家が少ないなどの課題もあり、十分な成果が得られていないのが現状です。今後は、公的機関と民間企業の連携強化が求められます。
M&Aによる事業承継の留意点
M&Aによる事業承継には様々なメリットがありますが、同時に課題やリスクも存在します。企業文化の違いや従業員の不安感、税務上の影響など、事前に十分な検討が必要不可欠です。
企業文化の違いへの対応
M&A後の最大の課題は、異なる企業文化の統合です。経営方針や業務プロセス、人事制度などが異なれば、摩擦が生じる可能性があります。
そのため、PMI(ポストマージャーインテグレーション)の実施が重要となります。綿密な計画と従業員への丁寧なコミュニケーションにより、企業文化の統合を円滑に進める必要があります。
従業員の不安感への配慮
M&Aは従業員にとって大きな不安要因となります。雇用や待遇の変更、企業文化の変化など、様々な不安が存在します。
経営陣は、従業員への十分な説明と理解の促進に努める必要があります。不安を払しょくすることで、モチベーションの低下を防ぎ、生産性の維持につなげることができます。
税務面での影響と対策
M&Aには税務上の影響が大きく、株式譲渡と事業譲渡では異なる税金が発生します。不動産の取得にかかる税金についても検討が必要です。
そのため、M&A検討の初期段階から、専門家によるアドバイスを受けることが重要です。適切な手法を選択し、節税対策を講じることで、コストを抑えることができます。
まとめ
事業承継におけるM&Aは、後継者不在の問題解決や事業の持続的成長のために、ますます重要な選択肢となってきています。企業は、M&Aのメリットやリスクを十分に理解し、適切な戦略を立てることが求められます。
一方で、政府や自治体、金融機関、民間企業などが連携してM&Aを支援する動きが広がっており、中小企業にとってもM&Aへの参入障壁が下がってきています。事業承継に悩む経営者は、様々な支援制度を活用しながら、M&Aも含めた最善の選択をすることが重要です。
よくある質問
M&Aによる事業承継のメリットは何ですか?
M&Aによる事業承継のメリットは、後継者不在の問題を解決できること、従業員の雇用維持と取引関係の継続が可能になること、両社のシナジー効果によって事業の発展や拡大につながることです。
近年のM&Aによる事業承継の実績はどうですか?
近年、政府による後押しもあり、M&Aによる事業承継の件数は増加傾向にあります。2022年の国内M&A件数は過去最高の5,119件となり、そのうち事業承継型のM&Aは748件で前年から6%増加しています。
M&Aによる事業承継を行う際の留意点は何ですか?
M&Aによる事業承継には、企業文化の違いへの対応、従業員の不安感への配慮、税務面での影響と対策など、事前に十分な検討が必要不可欠です。
M&Aによる事業承継を支援する制度はありますか?
政府は事業承継税制の拡充や事業承継支援センターの設置など、中小企業のM&Aを後押しする施策を講じています。また、各自治体や中小企業基盤整備機構、民間のM&A仲介会社などが支援を行っており、M&Aへの参入障壁が低くなってきています。